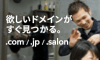鶏頭、鶏冠とも表記されるケイトウは秋の季語ではあるが、実は5月から10月にかけて長い花期をもつ。今は暦の上では秋であるが、連日35度以上の真夏日が続いている。にもかかわらず近隣の花屋にはケイトウの鉢植えが並んでいる。店頭に置かれた鉢には強い日差しが当たることもあるようだが、特に問題はなさそうだ。
この植物の原産地はアジアもしくはアフリカの熱帯と考えられ、本来暑さには強いようだ。そのため夏の園芸種としても歓迎されており、しかも秋まで楽しめるのだからよい。逆に寒さには弱いので冬越しはできず、あくまで一年草の扱いである。
万葉集には「カラアイ」として登場する。「韓藍」ということだろう。すでに園芸植物になっていたようで、山上憶良の歌に、
我がやどに韓藍蒔き生ほし枯れぬれど懲りずてまたも蒔かんとぞ思ふ
がある。カラアイには恋人の存在の寓意があるといわれているが、やど(邸前の庭)にカラアイを播種することがあったことをこの歌は教えてくれる。この花の鮮やかさは恋人の面影に比するにふさわしかったのかもしれない。
同じ万葉集の、
恋ふる日の日長くしあれば我が園のからあいの花色出でにけり
ここも園芸種とみられるケイトウだ。そしての花の色合いは恋の歌にふさわしかったのだろう。
鶏頭の十四五本もありぬべし
という正岡子規の句は賛否両論ある。子規がこれを作ったのは1900年のことであり、早逝した俳句創始者ともいえる人物がこの世を去る2年前の作だ。写生の論を主張した子規にとって十四五本という曖昧さや「ぬべし」という推量表現が観念的だと考えられる理由になっている。でも、この作品の感動の中心は鶏頭そのものにあり、それが複数ある。手指にも足りないほど多くということで、鶏頭のもつエネルギーのようなものに圧倒されていることをいうのだろう。子規の人生と絡めてしまうと余計に痛切な意味を感じるが、それを入れなくともいい句である。
鶏頭は古来から人の心を揺さぶる力を持っていた植物である。