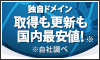古典文法を学ぶときいくつかの難所というべき項目がある。助動詞の用法の識別はその一つだろう。助動詞は日本語を日本語らしくする品詞の一つである。文の細かな意味や感覚を表現するのに助動詞が大きな役割を果たすからだ。現代語と比較しても古典の助動詞は種類が多く、なおかつ細かな使い分けがなされる。それを完全に習得することは難しい。
国語の教員であれば助動詞についてある程度は説明できなくてはならない。でも、文法のテストに答える程度であればあまり難しく考えすぎない方がいい。また、古文の読解のときにも助動詞の用法を厳密に言い分ける必要はない。多くの場合、いくつかの用法の境界にあり、よりどの要素が強いかというくらいの違いである。
今回は多義をもち、使用頻度の高い「る」「らる」について考える。
「る」と「らる」は同じで、いずれも動詞の未然形に接続する。「る」「らる」の直前に「a」の音があれば「る」を使い、なければ「ら」を加えて「らる」とする。だから、「走る」に「る」「らる」をつけるときは「走ら(未然形)」に「る」をつけるし、「起きる」につけるときは「起き(未然形」には「ら」を挟んで「る」をつけて「起き・ら・る」となっている。「ら・る」を一語として考えたのが「らる」という助動詞だ。ちなみに、これは現代語の「れる」と「られる」にも共通するが、現代語では「られる」の「ら」を落としてしまう「ら抜き言葉」が普通に使われており、「見れる」「食べれる」に違和感を覚えない人の方が多くなっている。
この「る」「らる」には4つの用法(これを文法の時間では「意味」ともいう)がある。思い出していただきたい。①自発、②可能、③受身、④尊敬の4つだ。受験生には「自可受尊(じかじゅそん)」とおぼえさせる。なんとなく語呂がいい。印象的な感想で根拠はないがこの順番で使用頻度が高いとも思うからこの暗記法は無意味ではないかもしれない。
「自発」は<自然と~れる>と訳す用法で、例えば昔のアルバムを開いて、過去のおのれの姿を見たとき、思わず「なつかしいなあ、あの頃はよかったなあ」などと勝手に感情が湧き出すときのことをいう。文法用語ではこれをそっけなく「自発」という。意図しなくてもやってしまうことである。性格上、感情を表す動詞に付属して使われる。「思ふ」「しのぶ」「泣く」「笑ふ」などと組み合わされる。識別するときにもこれが指標となる。
「可能」は<できる>の意味になる場合だ。ただし、平安時代までの用例のほとんどは打消しの言葉とともに使われるから、実際には「~れ(られ)・ず」の形で出ることが多い。打消「ず」は非常に不規則な活用をするし、打消の意味を持つ後には「じ」「まじ」などの助動詞や「で」という接続助詞もあるので戸惑うこともあるかもしれない。これは打消しとセットになって、自分ではどうしようもできない状況をいうときに使われていたのだろう。自発の逆に当たる。ただし、鎌倉時代以降は肯定文の例もある。
「受身」は<される>と訳すもので、この助動詞の大切な役割の一つである。訳すときに「~に」という動作主が想定される場合に使われる。「起こさる」は「~に、起こされる」ということであり、この「~に」の意味が必要な場合が受身ということになる。古典ではこの動作主はたいてい生物であり、現代のように抽象的な語が主語になるもの、たとえば「ストレスに苦しめられる」のような例は少ない。動作主がほかでもない自分自身の感情にあるときには「自発」となるのだ。
「尊敬」は<なさる>と訳すもので、主語が貴人である場合に使われる。おそらく自分とは距離を置いた存在が、自分の意志とは無関係にものごとをするという意味から自発的な意味合いもあり、その動作を直接的な作用を受けなくても影響があるという点で受身的な意味もあるといえる。
4つの用法はつながっていて実は自分の意志や目的とは無関係に物事が進行するときに起きる感情を表現するときに使用されていたのではないか。実際の用法の中で様々な変化形が生まれ、多様に使われるようになっているのだ。最初にもふれたが文法的意味(つまり用法)はあくまで便宜的な分節に過ぎない。生徒諸君にもこの点を知っておいてもらった方が本当の古典が理解できるようになるのかもしれない。